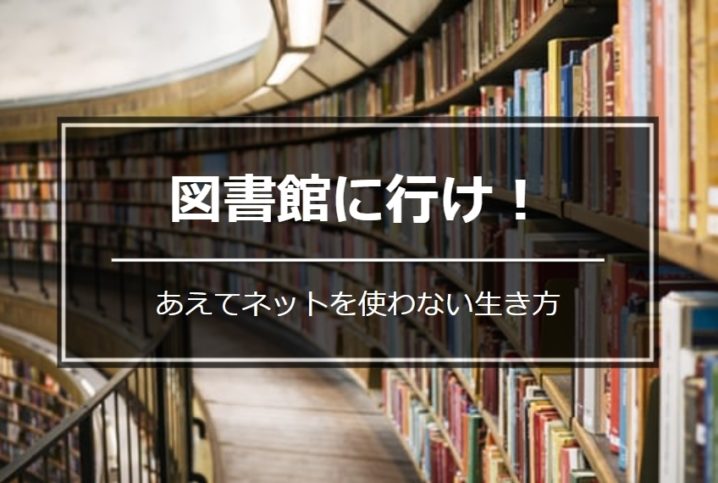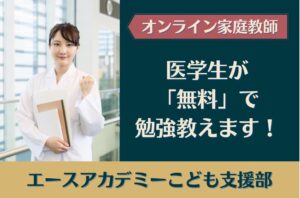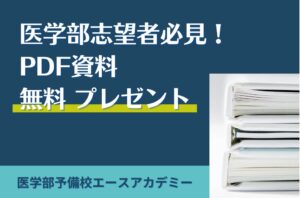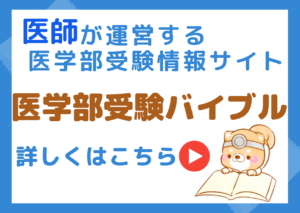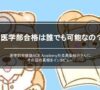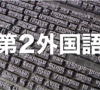どうも。近ごろ海外ドラマを見はじめたK太朗です。
さて、今は小学生でもスマホが与えられたり、パソコンを使わせてもらったりする時代です。そんな中で、あらゆる情報が手に入るインターネットは、とんでもなく便利に見えることでしょう。
しかし、中学入学以降三年以上ネットを使ってきた筆者は(といっても社会人の方々と比べれば短いですが)、ネットでは手に入らない情報があると知っています。
なぜその情報はネットで手に入らないのか、そしてどうすれば手に入るのかを、特にこれからネットづきあいを始める世代向けに、この記事で解説します。
「ググる」の落とし穴
Wikipediaをやめた理由
唐突ですが、ぼくはちょっと前まで、一か月以上Wikipediaを一切見ていませんでした。それも、意識的に見ないようにしていました。
なんだってそんな妙な制約を自分に課していたのか、よくわからない方も多いでしょう。
実はぼくも、以前は「Wikipediaサーフィン」するほどWikipediaを愛用していました。気になることがあればすぐWikipediaで調べ、調べた記事に出てきた気になるリンクを開き、さらにその記事に出てきた気になるリンクを開き、という具合です。
これでは時間の浪費になるだけだから、いっそWikipedia自体見るのをやめよう、というのが、「断Wikipedia」を始めた経緯です。
しかし、歴史には「直接的な理由」だけでなく、必ず「本質的な理由」が存在します(これは歴史の教師からの受け売りですが)。
その本質的な理由こそが、この記事のテーマです。
ネットの情報は「薄い」
この話のWikipediaは、インターネットそのものを象徴しています。
そう言えるポイントはいくつかあって、具体的には、
・あらゆる情報が簡単に手に入る
・一覧性がある
などです。確かに、世界中を繋げている情報網=インターネットの特徴と合致しています。「これぞ文明の利器!」という感じですね。
しかし、これらの大きなメリットの裏返しとして、重大な欠点をも孕んでいます。
それは、情報に厚みがないことです。
つまり、ネットの情報は、「広くて薄い」のです。
なんだか急に抽象的な話になってしまったので、次項以降でわかりやすく解説していきます。
本 vs インターネット
情報の形について
先ほど「ネット情報は厚みがない」といいました。
この「厚みがない」という部分を平たく言うと、「まとまりがない、筋道が通っていない」ということになります。
そしてその逆の、まとまりがあり、筋道が通った情報を提供してくれるのが、本です。
もちろん本のジャンル、形式などにもよりますが、多くの本には筆者の主張があり、その主張を補強するために様々な事実が並べられています。しかも、多くの本は一年、場合によっては何年もかけて、筆者と編集者が綿密に練り上げたものです。
それゆえ本からは、単なる情報の羅列ではなく、人を強く動かす力を持った物語を得ることができます。
これがインターネットとの大きな違いです。
ネットで調べられることって?
とは言いつつ、ぼくもネットで情報を発信している身ですし、ネットにも多くのメリットはあります。
重要なのは、何でもかんでもググってしまうのではなく、しっかりと見極めをすることです。
では何をネットで調べて何を本で調べればいいのかということですが、そもそも「調べる」という言葉の範囲はかなり広いので、これはある程度経験が必要かもしれません。いちおうざっくりと基準をお話しすると、
・いろいろな意見を知りたいとき、最新の情報を知りたいとき、簡単な事柄を調べたいときなど → インターネット
・一つの物事について興味があり、深く知りたいとき、深く考えたいときなど → 本
という感じです。文字にしてしまえば単純で、なんとなくお分かりいただけると思います。
では、「これは本で調べたほうがいいな」と思ったときにどうすればいいのか。次章で解説していきます。
図書館に行け!

図書館に行こう
本を読みたいなら本屋があるじゃねえか、と思われるかもしれませんが、こういう場合は図書館に行きましょう。理由はいくつかあって、
・リラックスできる
・あらゆるジャンルごとに本が均等にあり、整理されて置かれている
・無料なので、気兼ねせずいくらでも読める(途中で飽きてもいい)
などなど。
ちなみに筑駒はなぜか図書館の司書さんがTwitterアカウントを運用しています。筑駒の生徒が普段どんな本を読んでいるのか、外部の人にも分かるように情報発信をしてくれているので、ぜひご覧ください。
特に、自由に使えるお金の少ない我々にとっては、本屋のようにお金の心配をすることなく、上限冊数(だいたい20冊くらい?)までいくらでも借りていけるのがうれしいですね~。
デメリットとしては期限があることですが、これは延長もできるのであまり気にせずやっていきましょう。
それでは、これ以降は具体的な図書館の使い方を解説していきます。
メモを取る習慣
まず、ネットの情報ならば思い立った時すぐにスマホで調べればOKですが、その点図書館は行くのに時間もかかり、いつでも行けるわけではありません(この点では完全に本の敗北です)。
ではどうすればいいのかというと、ふだん生活していて、「これはもっと深く知りたいな」「これはネットじゃ調べられないな」という事柄があった場合、すぐにメモを取るようにしましょう。
やり方は何でも構いません。ぼくの場合、図書館のホームページで関連していそうな本をマイリストに追加する、という方法を使ったりしています。こうするとどんな本が図書館にあるかもわかるので、一石二鳥です(結局ネットの恩恵にもあやかってるわけですが)。
そして、メモが溜まってきたら、あるいは暇になったら、図書館に行く習慣をつけましょう。メモを読みながら良さそうな本を探して、いくつかを手に取り、館内の椅子でゆっくり読んでいるだけで、時間があっという間に過ぎていきます。
実に優雅な休日の過ごし方ではありませんか。
図書館がどうしても肌に合わないという方は、大型書店を巡ってみるのもおすすめです。中学受験を始めとする参考書はもちろん、地理・歴史や科学分野で知的好奇心を満たす本がたくさん揃っています。営業時間も図書館より長いことが多いので、思う存分入り浸れます。詳しくは以下の記事をご覧ください。
偶然の出会い
ところで、はじめから検索機能を使って一つの本にターゲットを絞るのもいいですが、ぼくはなんとなく関連していそうな棚を探していくのが気に入っています。
というのも、自分では想像できないような本に出会うことが出来るからです。
たとえばあるとき、民俗学になんとなく興味を持っていて、その棚を探していたら、『神隠しと日本人』という本を見つけたことがありました(リンクはこちら)。
これは、神隠しという現象がどのように言い伝えられてきたのか、そしてそれが地域社会においてどのような役割を果たしてきたかを説明した本なのですが、題名だけでもう面白そうな本だと思いませんか(笑)
そして、実際読んでみてもなかなかに興味深い本だったのですが、もしこのような探し方をしていなければ、永遠に出会えなかった本かもしれません。
最後に
ぼくなりに抱いてきた、ネットへの違和感と図書館への思いを形にしたい、そう考えてこの記事を作り始めたのですが、皆さんには伝えることができたでしょうか?
この記事を機に、少しでも行動を変えてくれる人が現れればうれしい限りです。
最後に、下のような関連記事もありますので、是非読んでみてください。
おすすめの大型書店シリーズ第2弾
先ほどご紹介したジュンク堂池袋店に続くおすすめの大型書店シリーズ。第2弾は新宿紀伊國屋書店です。こちらもジュンク堂書店に負けず劣らずの規模を誇っています。
圧巻の東京都立中央図書館
続いて男子御三家の麻布学園の目と鼻の先にある都立中央図書館をご紹介します。こちらも日本最大級の蔵書量を誇り、調べ物をするときに重宝する図書館です。近くには有栖川公園という自然豊かな公園もあり、勉強や調べ物の息抜きにも最適です。
この記事を書いたライター
 インタビュー2021年11月20日【13の質問】あなたが医学部受験を決める理由&受かる人の特徴とは?-医学部受験塾ACE Academy社長髙梨裕介さんインタビュー
インタビュー2021年11月20日【13の質問】あなたが医学部受験を決める理由&受かる人の特徴とは?-医学部受験塾ACE Academy社長髙梨裕介さんインタビュー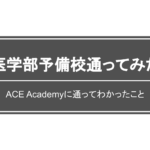 受験対策・科目別勉強2021年9月18日「医学部予備校ACE Academy」体験記
受験対策・科目別勉強2021年9月18日「医学部予備校ACE Academy」体験記 勉強法&生活スタイル2021年7月29日【超必見】楽器練習ガチ勢へ。
勉強法&生活スタイル2021年7月29日【超必見】楽器練習ガチ勢へ。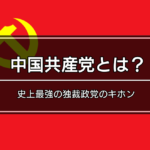 豆知識・思うこと2021年7月1日【創立100周年!】中国共産党ってどんな党?
豆知識・思うこと2021年7月1日【創立100周年!】中国共産党ってどんな党?